導入
飲食店経営の成功可否は、立地で8割が決まる──そんな言葉があるほど、立地選びは開業前の最重要事項です。本記事では、実際に失敗例や成功事例を交えながら、飲食店の立地選びで確認すべき5つのポイントを解説します。
背景・課題
立地を誤ると、どれだけ料理が美味しくても集客が続かないという現実があります。特に家賃の高さに惹かれて人通りの多いエリアを選んでも、ターゲット層とズレていれば売上は伸びません。また、居抜き物件などの好条件に見えても「客層・アクセス・視認性・競合」といった要素の精査が不足しがちです。
実践ステップ
ステップ1:ターゲットに合わせた人流調査を行う
自店舗のターゲット(例:30代女性、ランチ中心)に合わせて、曜日・時間帯別の人通りを現地調査します。たとえば平日ランチ帯にサラリーマンが多いエリアなら定食屋や弁当屋が向いており、夜間や週末にファミリー層が集まる地域なら居酒屋やファミレス系の方が親和性が高まります。
ステップ2:視認性と導線を現地で確認する
通りから店舗が見えやすいか、駅からの導線はわかりやすいか、雨の日や夜間の人流はどう変化するかなどを複数の時間帯に分けて確認しましょう。2階店舗やビル奥まった場所の飲食店は認知コストが高いため、集客に追加の広告費が必要になるケースも。
ステップ3:競合店舗と補完関係を意識する
周辺にある同業他社だけでなく、補完関係にある業種(例:カフェの近くに美容室)があるかもチェックしましょう。競合が強すぎる場所は避けつつ、相乗効果を生みやすい立地はむしろ集客にプラスになります。
ステップ4:時間帯別の需要特性を分析する
飲食業は「昼型」「夜型」「通し営業型」によって適する立地が変わります。たとえばオフィス街は平日昼がピーク、住宅街は夜や週末の売上が主軸です。どの時間帯に稼ぎたいのかを先に決め、その特性にマッチしたエリアを選びましょう。
ステップ5:固定費とのバランスを確認する
理想の立地でも、家賃が月商に対して重すぎれば失敗リスクが高まります。目安は「家賃:月商の10%以下」です。立地にかけるコストと回収可能性をデータと事例で見積もる視点が欠かせません。
ツール紹介
人流データが見られる『Location AI Platform』
エリアごとの時間帯別の通行量や人の属性を視覚的に分析できるツール。ターゲットに合った場所を定量的に選定可能。
→ https://location-ai.jp/
周辺業種や競合を調査する『Googleマップ×MEOチェッカー』
MEO順位や近隣飲食店のレビュー傾向、混雑時間などを把握でき、差別化戦略にも活用可能。
→ https://meo-checker.jp/
よくある質問
Q1. 駅近の物件は本当に有利ですか?
駅近は人流が多く一見有利に見えますが、家賃が高くターゲット層が分散しやすいため、必ずしも正解ではありません。目的来店型業態(ラーメン、焼肉など)は少し離れた場所でも成功例があります。
Q2. 居抜き物件はどう判断すればいい?
設備の状態とターゲット層との相性、前テナントの評判を必ず確認しましょう。初期費用は抑えられても、マイナスイメージがついた物件はリスクもあります。
Q3. 商業施設内の立地はおすすめ?
モールや駅ビルなどの施設内は集客力がある反面、営業時間や販促の制約、売上歩率などの条件に注意が必要です。自由度とのトレードオフを理解した上で検討しましょう。
まとめ・アクション
立地選びは、現地調査とデータ活用のバランスが成功の鍵です。本記事で紹介した5つのチェックポイントをもとに、数字と感覚の両面から検証し、後悔しない立地選びを実現しましょう。人流調査や視認性チェック、競合マップの整理は最低限行い、感覚だけに頼らず、ツールや事例も活用してください。

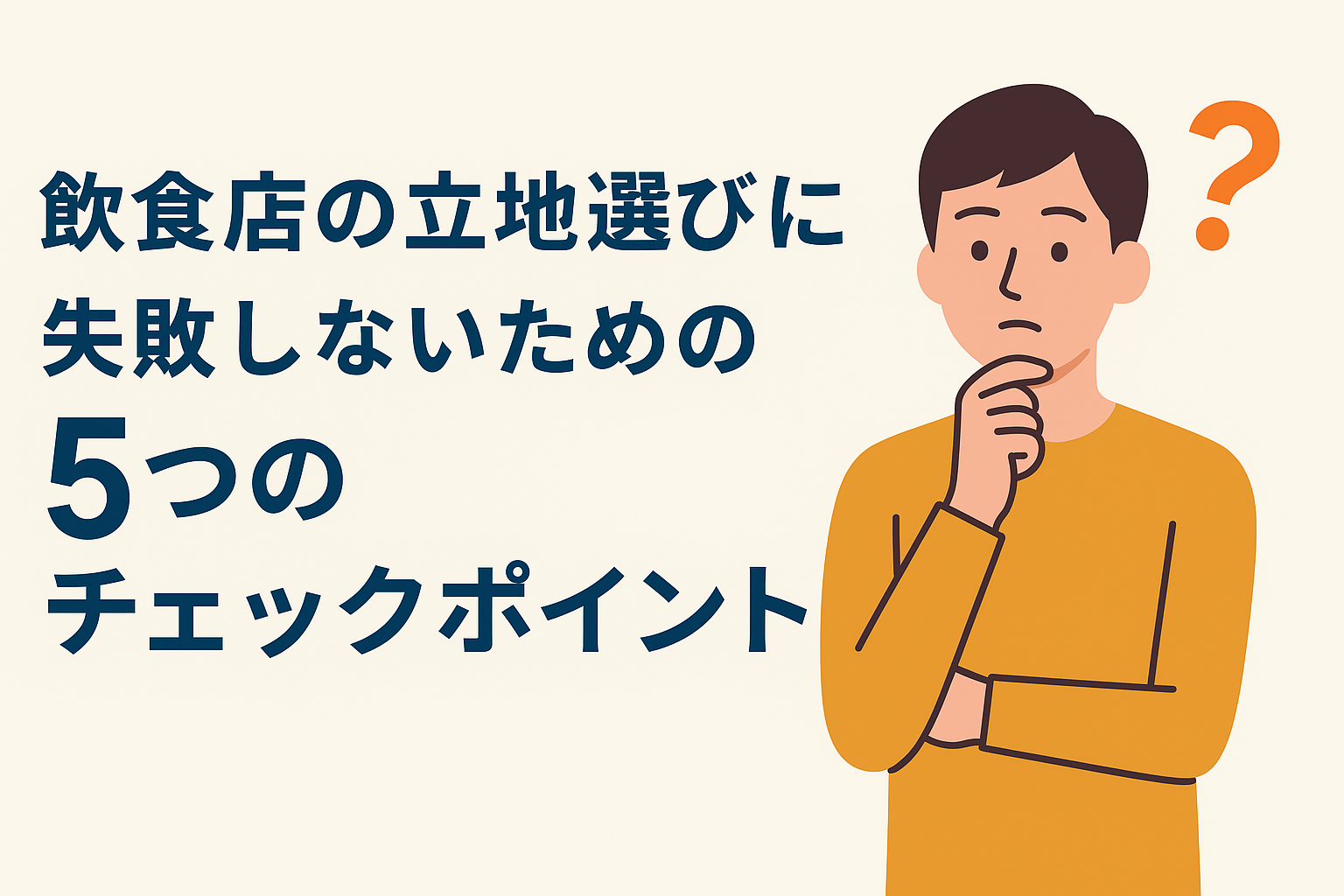



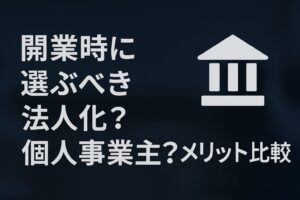



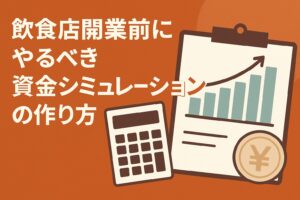

コメント