はじめに
「店長が一番遅くまで残り、一人ですべての業務を抱え込んでいる」 「あの店の店長は優秀だが、彼が休むと店が回らない」 「新人が入っても、店長が忙しすぎて教育できず、すぐに辞めてしまう」
これらは、多くの飲食店オーナーが抱える深刻な悩みです。 「名プレイヤー」である優秀なスタッフを店長に昇進させた結果、業務過多で疲弊させてしまうケースは後を絶ちません。
その根本原因は、店長に「プレイヤー」としての能力だけでなく、「マネージャー」としてのスキルが求められるようになるからです。そして、そのスキルは、教えて学ばなければ身につきません。
この記事では、疲弊する店長を救い、強いチームを作るために不可欠な「マネジメントスキル」とは何か、そしてそれをどう育成するかについて、具体的な研修事例やOJTのポイントを交えて徹底解説します。
1. なぜ「名プレイヤー」を店長にすると失敗するのか?
多くの飲食店では、現場のオペレーション能力が最も高いエーススタッフが店長に昇格します。しかし、そこで壁にぶつかります。
- 「自分でやった方が早い」という思考 優秀なプレイヤーであるほど、他人に任せるよりも自分でやった方が早いと感じ、アルバイト教育を後回しにしがちです。
- 「背中を見て学べ」という属人化 自分がそうであったように、技術は「見て盗む」ものだと考え、マニュアル化や言語化を怠り、結果としてZ世代のスタッフが定着しません。
- 「プレイング」で手一杯になる 本来やるべき「マネジメント業務(売上管理、シフト作成、育成)」に時間が割けず、目の前の接客や調理に追われ、店長自身がボトルネックとなります。
人が辞めない飲食店の共通点は、店長が「スーパープレイヤー」であることではなく、店長が「チームを機能させる監督(マネージャー)」であることです。この役割転換を促すのが「研修」の目的です。
2. 飲食店店長に必須の4大マネジメントスキル
店長を育成するとは、具体的にどのスキルを伸ばすことでしょうか。飲食店店長に求められるスキルは、大きく分けて以下の4つです。
① 計数管理スキル(守り)
感覚的な「忙しかった」ではなく、数字で経営状態を把握し、改善する能力です。
- PL(損益計算書)の理解:売上、原価、人件費、利益の構造を理解する。
- FLコストの管理:食材原価(Food)と人件費(Labor)を適正な比率にコントロールする。
- 行動への反映:売上予測AIなどを参考に、売上目標から逆算して「今日はあと何組必要か」「客単価をどう上げるか」を考え、フードロス削減など具体的な行動に落とし込む力。
② 人材育成スキル(育成)
自分がいなくても現場が回る状態を作る、最も重要なスキルです。
- OJT(On-the-Job Training):体系立てた教育カリキュラムに基づき、新人スタッフを即戦力化する技術。
- ティーチングとコーチングの使い分け:知識を教える「ティーチング」と、相手に考えさせ引き出す「コーチング」を使い分ける。
- マニュアル化:業務を言語化・マニュアル化し、誰がやっても一定のクオリティを保てる仕組みを作る。
③ チームビルディングスキル(攻め)
個々のスタッフを「集団」から「チーム」に変える能力です。
- ビジョンの共有:「自分たちの店は、お客様にどんな価値を提供するのか」という目的意識を統一する。
- 動機付け(モチベーション管理):スタッフの強みを見つけ、適切な評価制度や朝礼での声かけを通じてやる気を引き出す。
- コミュニケーションの仕組み化:定期的な面談や日報などを通じて、風通しの良い職場環境を維持する。
④ 課題発見・解決スキル(改善)
「なんとなく」の問題を放置せず、具体的に改善(PDCA)を回す能力です。
- ボトルネックの特定:「なぜ予約の電話が繋がらないのか?」「なぜ特定の曜日にクレームが多いのか?」といった根本原因を突き止める。
- 業務改善:特定した課題に対し、シフト運用を見直すなど具体的な業務改善策を立案し、実行する。
3. マネジメントスキルを伸ばす研修・育成事例
これらのスキルは、座学だけでは身につきません。「知識(Off-JT)」と「実践(OJT)」を組み合わせることが不可欠です。
事例1:【内部研修】他店舗の成功事例をインプットする「店長会議」
- 目的:計数管理スキル、課題解決スキルの向上
- 方法:
- 月に一度、全店長を集めた店長会議を実施。
- 単なる報告会ではなく、各店が「今月の成功施策(数字的な成果含む)」と「失敗施策(なぜ失敗したか)」を具体的に発表。
- 例:「Google口コミを増やすQRコードを導入し、口コミ数が1.5倍になった」「季節メニューの原価計算を間違え、利益率が圧迫された」
- 効果:
- 自分の店舗だけの狭い視野から解放され、他店の成功事例をすぐに自店で実践できる(横展開)。
- 数字に基づいた発表が求められるため、計数管理への意識が強制的に高まる。
事例2:【内部研修】「ジョブローテーション」で視点を強制的に変える
- 目的:チームビルディング、人材育成スキルの向上
- 方法:
- 特に「自分のやり方」に固執しがちな中堅店長を、あえて「売上が好調な店舗」や「外国人スタッフが多い店舗」など、環境が全く異なる店舗へ1ヶ月間「研修」として異動させる。
- 効果:
事例3:【外部研修】外部セミナー +「実践レポート」の義務化
- 目的:人材育成スキル(特にコーチング)の向上
- 方法:
- 外部の「リーダーシップ研修」や「コーチング研修」に店長を派遣する。
- 重要:研修に行かせっぱなしにせず、必ず「研修内容を自店でどう活かすか」という実践レポートを提出させる。
- 例:「部下を指導する際、今までは『なぜできないんだ』と詰めていたが、研修後は『どうすればできると思う?』と質問するよう変更する」
- 効果:
- インプット(知識)をアウトプット(実践)に繋げる意識が生まれる。
- オーナーや本部が、店長の「やる気」や「理解度」を客観的に把握できる。
4. 日常業務(OJT)で店長のマネジメントスキルを伸ばすコツ
研修は「きっかけ」に過ぎません。日常の業務の中でオーナー(SV)がどう関わるかが、店長の成長を左右します。
- コツ1:「どう思う?」と問いかけ、考えさせる 店長から「スタッフが辞めたいと言っています。どうしましょう?」と相談された時、すぐに「こうしろ」と答えを与えてはいけません。「店長はどう思う?」「原因は何だと思う?」と必ず問い返し、店長自身に答えを考えさせるクセをつけさせます。
- コツ2:「数字」で会話するクセをつける 「昨日忙しかったです」という報告には、「具体的に、客数は?売上は?先週比は?」と数字で返すことを徹底します。「データドリブンな経営が基本」という文化を根付かせます。
- コツ3:意図的に「権限移譲」し、小さな失敗をさせる 「今月のキャンペーン企画、店長に任せる」「アルバイトの採用面接、店長が判断していい」。最初は失敗するかもしれません(例:採用NG質問をしてしまう)。しかし、責任を持って判断させた後の「振り返り」こそが、最大の学びの場となります。
- コツ4:本部が「管理職育成プログラム」を持つ 店長の「その先」のキャリア(SV、エリアマネージャー)を提示することも重要です。会社として管理職を育成する明確なプログラムがあることを示し、店長自身の学習意欲を高めます。
まとめ
飲食店の店長育成は、企業の店舗展開戦略における最重要課題の一つです。
「スーパープレイヤー」を「名マネージャー」に変えるには、本人の努力任せにするのではなく、会社として体系的な「研修(Off-JT)」と「OJT」の仕組みを提供することが不可欠です。
まずは、あなたの店の店長が「プレイヤー業務」と「マネージャー業務」のどちらに時間を使いすぎているか、現状を把握することから始めてみませんか。




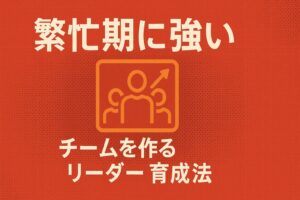
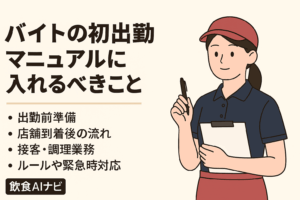
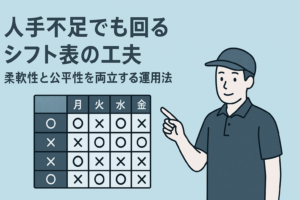
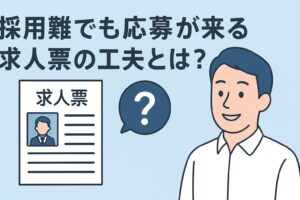
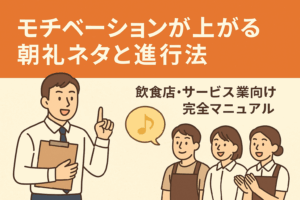
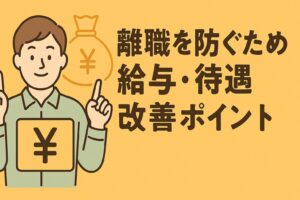

コメント