導入:立地の“良し悪し”は、想像以上に経営を左右する
「人通りは多いはずなのに、なぜか客足が伸びない…」
「駅近だから安心していたが、思ったほどリピーターが定着しない…」
このような悩みは、実は“立地の選定視点”に原因があることが少なくありません。
飲食店の成功において、立地は「味」や「接客」と同じくらい重要な要素。にもかかわらず、多くの開業者が家賃・人通り・駅距離だけで判断してしまい、導線や競合、滞在心理などの本質的な視点を見落としてしまいます。
本記事では、開業前に必ずチェックしておきたい**“見落とされがちな立地の5つの落とし穴”**を、交通導線と競合視点から具体的に解説します。さらに、実際の店舗での立地失敗・成功事例を交えながら、開業前にやるべきリサーチ方法やツールもご紹介します。
1. 「人通り=集客」ではない|“通行量の質”を見極める
よくある誤解
「この道は人通りが多いからきっと繁盛するだろう」
しかし実際には、
- 学生の通学路(飲食には繋がらない)
- ビジネスマンの“通過点”(ランチ需要のみ)
- 観光客の集中エリア(リピートに繋がりにくい)
など、“通るけれど止まらない”人通りである可能性も高いのです。
チェックポイント
- 平日/土日、昼夜の時間帯別の観察
- その道を歩く人が「飲食を目的としているか」
- 周辺の飲食店が混雑しているか(需要との整合)
実践リサーチ法
- スマホで1時間動画撮影(人の流れを分析)
- カウンターを持って通行者数を手集計する
- GoogleストリートビューやSNSで周辺の人の投稿を分析する
2. 駅からの距離より「出口・導線」が重要
見落としがちな構造的要因
- 駅に近いが「反対側出口から遠い」ため集客困難
- 階段や交差点が多く「気軽に立ち寄れない」動線
- 地下階・2階などの視認性の弱さ
特に都心部では、**「駅近だけど集客に苦戦している店舗」**が多くあります。
実際、店舗展開時のエリアマーケティング基本|立地選定の失敗を防ぐチェックリスト でも、出口動線と導線把握の重要性は強調されています。
対策
- 店舗前から駅出口までの実地動線を確認(徒歩動画など)
- 看板・誘導導線がどこからも見えるかの視認性調査
- 雨の日・夜間・混雑時にもアクセスしやすいかを確認
- Googleレビューで「場所がわかりづらい」などの声がないかを確認
3. 同一通りの“競合密度”と“ターゲットの違い”
注意すべき競合とは?
- 同じジャンルの店舗が密集している
- 同価格帯・同時間帯に営業している
- Googleレビューなどで高評価の店が近くにある
競合が多すぎると、“比較される立場”になり、初期集客が難航します。
ただし、競合店が存在することで「人が集まるエリア」として成立している場合もあるため、ポジショニングの見極めが重要です。
対策
- 周囲の競合をGoogleマップ・食べログで調査
- メニュー・価格・内装の差別化ポイントを設計
- 「比較されること」を前提に、明確な強みを持つ
このアプローチは、ファンを作る飲食店はここが違う!ブランディングの実践法 とも関連性が高いです。
4. “何のための店か”が立地に合っていない
例えば、
- 「昼メインの定食店」なのに周囲はオフィスゼロ
- 「ディナー高単価」なのに治安が悪く夜道が暗い
- 「女子向けカフェ」なのに通行量が男性中心
こうした“立地と業態のズレ”は、どれだけ店の完成度が高くても結果が出ません。
対策
- 想定客層と一致する時間帯・曜日に現地調査を行う
- 駅改札や信号など“待ち時間のあるポイント”との距離感も確認
- SNSで近隣の顧客層がどんな投稿をしているかチェック
- 開業予定の時間帯に現地で実際に「滞在してみる」こと
5. 「視認性・印象」にお金をかけないのは致命傷
立地が完璧でも、
- 看板が見えにくい(色・文字・サイズ)
- 外装が目立たず存在感がない
- 照明が暗く“営業しているかわからない”
このような状態では“存在していないのと同じ”です。
店舗があることに気づかれなければ、集客導線も、口コミも、SNS映えも起きません。
視認性においては、口コミしたくなるお店の共通点とは?紹介が生まれる店舗設計 も参考になります。
対策
- 看板は「遠くからも見える+近くで読める」デザインに
- 外装に“記憶に残るフック”をつける(例:ネオン・装飾)
- 昼夜で印象が変わらないよう、照明・照度も調整
- 「SNSで映える店構えか?」を事前に検証
まとめ:立地判断は「現地+生活導線+競合」の三位一体で考える
立地の良し悪しは、表面的な条件だけでは判断できません。
- 通行量の質は?
- 導線のストレスは?
- 競合の数と強さは?
- ターゲットと一致した時間帯に人がいるか?
- そもそも視認されているか?
こうした問いを“現地の目”で確認し、「数字」「生活導線」「感覚」のすべてを加味した判断が、繁盛立地への近道となります。




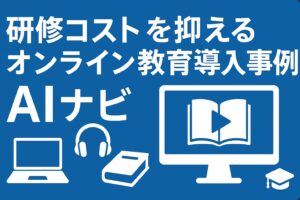

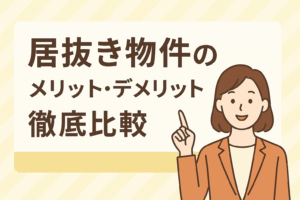



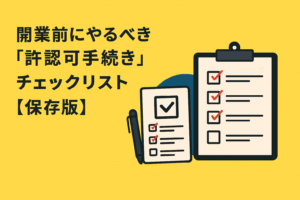
コメント