はじめに:利益が出ない本当の理由は“食材のムダ”かもしれない
飲食店を経営していて「売上はあるのに利益が出ない」と感じたことはありませんか?
原価率や人件費をいくら見直しても、なぜか利益が残らない…。
その背景にあるのは、見えないコスト=食品ロスかもしれません。
廃棄された食材だけでなく、仕入れにかかった原価、仕込みや保存に費やした人件費、冷蔵・冷凍のエネルギーコスト、さらには“売れなかったことで失った機会損失”も含めると、食品ロスの影響は非常に大きくなります。
本記事では、食品ロスの構造的な仕組みと、
それを解決するために現場で実際に取り組まれている仕組み化・AI活用の事例を詳しく紹介します。
食品ロスの主な種類とその原因
1. 廃棄ロス:発注や保存のズレによるロス
- 想定より売れなかったことで余った仕入れ食材
- 賞味期限切れや腐敗による廃棄
- 保存環境の不備で劣化
このような“在庫リスク”は、食材回転率を意識した発注と仕入れ管理で回避可能です。
たとえば、冷蔵庫内を棚卸しする際、スタッフがその都度在庫を把握する仕組みを作ることで、ムダを削減できます。
さらに、下記の記事では固定費全体の見直し視点からロスに取り組む方法も詳しく紹介しています:
飲食店の利益率を上げるために見直すべき固定費ベスト5
2. 調理ロス:仕込みや調理工程で発生するムダ
- 食材の切りすぎ・仕込みすぎ
- オーダーミスによる再調理
- スタッフごとの技術差による歩留まりの悪さ
これは調理マニュアルの整備やスタッフ教育の質に大きく左右されます。
とくに新人アルバイトにおいては、適切な教育フローがないと、必要以上の盛り付け・取りこぼし・無駄なカットが発生します。
このような育成の見直しには、
ChatGPTを活用した新人バイト教育マニュアル
が有効です。
3. 食べ残しロス:お客様に完食されない理由とは
- ポーションが多すぎる
- メニュー内容が冗長・飽きやすい
- 味の好みや偏りに対応できていない
この部分に注目することで、「提供する前提」から食べ残しを減らす設計が可能になります。
たとえば、シニア層や女性客に向けたハーフサイズ対応やセット内容の選択制が食べ残しの減少に直結します。
こうしたメニュー設計や満足度向上は、リピート客づくりにも貢献します:
紹介したくなるお店になるために必要な3つの要素とは?
成功事例① 和食店「旬菜やまもと」|在庫を“絞る”ことで年間96万円改善
- 背景:週末に向けた魚介類の仕入れが多すぎて毎週のように破棄
- 施策:
- 「使用量が読めない食材」をリストアップ
- 魚介は冷凍耐性のある部位に絞り、定番メニューとして回す
- スプレッドシートで「廃棄記録」「ロス率」「原価率」を日次で記録
- 成果:
- 月10万円→2万円まで廃棄コストを削減
- 原価率は32%→26%に改善
- 年間約96万円の利益改善に直結
成功事例② カフェ「Cafe Kotori」|AIによる来客予測で仕入れのズレを解消
- 背景:週末ごとの来客数ブレにより、焼き菓子などの大量ロスが発生
- 施策:
- TORETA Insight+Weather API+Googleカレンダーで来客予測を自動化
- メニューを冷凍可能パーツに分解し、食材ローテーションを見直し
- 週次レポートで予測精度と実来店数を突き合わせてPDCAを高速化
- 成果:
- 廃棄率60%削減(4万円→1.6万円/月)
- 利益率12%→18%に上昇
このような仕組みには、売上データ連動型AIツールが有効です:
売上ダッシュボードで店舗経営を可視化するAIツールまとめ
成功事例③ トラットリアK|スタッフがロスに主体的に取り組む文化づくり
- 背景:多店舗展開によるオペレーションの分散化で、ロス意識が薄れていた
- 施策:
- 毎日の「ロス報告」をLINEグループで共有(写真+数量+理由)
- 月次でロス率上位スタッフを表彰、給与反映に連動
- 「仕込み前に冷蔵庫棚卸しを行う」文化を定着させた
- 成果:
- 原価率30%→24%まで改善
- スタッフの在籍期間も平均10ヶ月→18ヶ月へ
人材の定着率を高める工夫としても、ロス削減文化は重要です:
スタッフ定着率を高める評価制度・運営ノウハウまとめ
食品ロス削減のための仕組み化ステップ3選
ステップ1:記録と可視化
- LINEやGoogleフォームで「何を捨てたか」を毎日ログ化
- 画像・理由・数量を必ず添えて、数値で分析できるようにする
ステップ2:発生原因の分類と傾向の分析
- 食材別の廃棄傾向、曜日や天候との相関性
- 誰が関与した工程か(調理者、仕込み担当など)
ステップ3:仕入れ・調理・提供の構造を見直す
- メニュー設計を簡素化し、ロス耐性を高める
- 冷凍保存可能な仕込みに変更する
- 予約数・天候・過去実績に基づいたAI予測を導入
よくある質問(FAQ)
Q. AIツールは高額で導入が難しいのでは?
A. 無料プランのあるものや、売上連動型のツールも多数あります。まずはTORETA Insightなどから試すのがオススメです。
Q. 冷凍食材を使うと味が落ちませんか?
A. 最近は「瞬間冷凍」や「真空パック冷凍」でほとんど味の劣化はなく、むしろ廃棄率の低下で料理の質も安定します。
Q. スタッフに記録を習慣化させるのが大変そうです
A. LINEグループに画像を投稿するだけでも良いので、まずは「記録する文化」を作ることが大切です。
まとめ:食品ロス削減は“我慢”ではなく“設計の見直し”
ロス削減というと「仕入れを減らす」「食材をケチる」といった“節約”的なイメージを持たれがちですが、実際はそうではありません。
むしろ、「設計・予測・提供」のすべてを最適化し、スタッフやお客様にとって気持ちのよい状態をつくることがロス削減の本質です。
正しく記録し、原因を見極め、仕組みに落とし込む。
その過程で得られるのは「利益」だけでなく、「現場の余裕」や「スタッフの満足」、さらには「お客様の満足度向上」にまでつながっていきます。




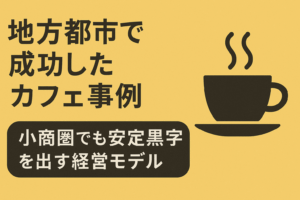

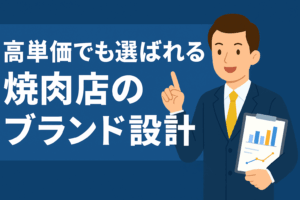
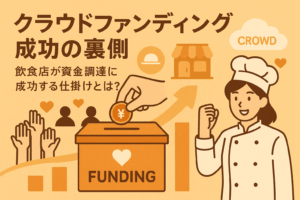

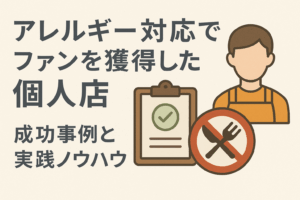

コメント